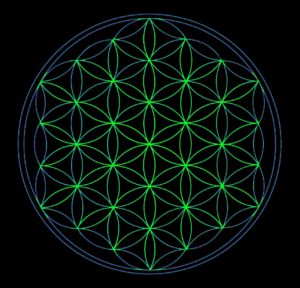3.タンパク質とはなにか
ここでは、異なる角度からタンパク質とは何かを考えてみたい。
現在、生物は火力など特殊な環境を除いて、物理学的に化学的に過酷な極限環境でも、一部はそれに適応しながら生息している。生物が新たな環境に進出する場合の先遣隊が、生物にとって最も重要な物質であるタンパク質である。新しい環境に適応できるように、自ら遺伝子を操作してアミノ酸組成や構造を僅かに変化させながら対応しているのである。
例えば、常温菌の酵素が耐熱性酵素に変化する場合、常温菌の培養温度を段階的に上げてゆくと、はじめは菌の増殖は抑えられるが、次第に増殖し、それに伴って酵素も培養温度に適応しながら耐熱性を増す。菌の培養温度がおよそ70℃の環境になると、酵素の耐熱度は20倍以上になるが、この時、酵素をコードする遺伝子の塩基配列の2か所に変異が観察されたという。このことは、酵素タンパクが耐熱性を獲得するには、二つの塩基さえ変異すればよいことになる。
一般に常温菌と超好熱菌は生息する環境が著しく異なるが、それぞれ同じ機能を持つ酵素タンパクの構造やアミノ酸組成を比較しても、構造的な変化はほとんど認められないことが知られている。このように、生物は極端に異なる環境にあっても、同じ機能をもつタンパク質の構造やアミノ酸組成には、その生物の形態や生息環境ほどの特徴的な違いは存在せず、仮にそのアミノ酸配列に著しい変異があったとしても、それは構造や機能に関係のない中立的なアミノ酸残基であり、立体構造への影響は僅かなものなのである。タンパク質という物質は、たとえ生物の形態や環境が著しく変化したとしても、構造や機能に必須なアミノ酸残基の僅かな変異で柔軟に対応できる性質をもっていると考えられ、だからこそこれまでの千変万化の地球環境下においても、生物は絶えることなく生存・進化し、さらにどんな極限環境へも進出することができたのだろう。
嫌気的状態から好機的環境への大転換で
千変万化の地球環境、その最大の例として、生命誕生後の地球大気環境の大変換がある。生命誕生後の大気は嫌気的状態にあり、生物はこの環境に適応しながら生存していた。この環境はしばらく続き、やがて光合成細菌の出現で酸素の発生が活発になり、海中や大気が一部を除いて好気的環境に変換するようになったといわれている。酸素は生命にとって危険な物質であったが、この好気的環境に一部の生物が進出していった結果、好気的環境条件の下でエネルギー獲得系に大量のATPが創生されるという結果がもたらされた。それには、天然タンパク質が総動員され、試行錯誤の末、TCA回路や酸化的リン酸化に関係するタンパク質が選択され、それらが連結した全く新しい複雑なATP獲得系を基盤とした、嫌気的大気よりもはるかに効率のよいATP生産機構が創生されたのである。
この機構を構成するタンパク質の中には、当時の細胞にはなく、原始前生物環境で一時的に生成され消失したタンパク性物質の情報を想起するものもあったと考えられる。私は、天然タンパク質の中に原始前生物環境で存在した短鎖ペプチド複合体の情報が利用されていたと考えている。即ち、TCA回路は代謝基質がクエン酸を経て水と二酸化炭素に徹底的に分解される回路であり、その過程で生成されたエネルギー源である水素は、NADHのかたちで内膜の電子伝達系に渡され、膜を挟んで水素濃度の勾配をつくり、その流れによりATP合成酵素がADPからATPを効率よく生産していたと考える。この場合のTCA回路に関与する一連の酵素タンパクの構造は、先に述べた構造が類似する解糖系の酵素タンパクとは違い、構造がまったく共通しておらず、寄せ集めだった感がする。原始前生物環境で意図性もなく無作為に創生されたトリカルボン酸やジカルボン酸を、後になって細胞が代謝基質の橋渡しをする酵素として選びだし、それぞれを統一的に連結し、回路が形成され、それがTCA回路となったのかもしれない。解糖系を構成する一連の酵素タンパクとTCA回路の一連の酵素タンパクの創生過程はお互いに一様ではなく、分子進化の隔たりを感じる。このように考えると、細胞が誕生して以来の新規タンパク質の創生も、原始前生物環境で創生された多数のタンパク質の原型である短鎖ペプチド複合体の情報を受けついだものと、まったく新しく創生しなければならないものとに分けることができるかもしれない。地球環境が嫌気的から好気的へ大変換した際、細胞におけるTCA回路や酸化的リン酸化のATP獲得系が比較的短期間で成立した理由は、そこにあるのではないかと考えている。また、もし仮に原始前生物環境で代謝系の酵素タンパクの原型が存在せず、細胞が従来から考えられている遺伝子の重複と変異で新規の多数の酵素タンパクをコードする遺伝子の一斉の創生だけで成立したとすれば、相当に長い進化の期間が必要とされたことが十分に考えられる。
以上のように、生物が全く新しい環境に適応するためには、その環境に適応する多くのタンパク質をコードする遺伝子を創生しなけばならなかった。しかし、この新しいエネルギー獲得系は大量のエネルギーを獲得する有利な系であったため、最終的にほとんどの生物が共有することになったと考えられる。その後、これら高いエネルギーをもつ単細胞生物は、やがて多細胞生物に進化し、地球上に多様な生物の繁栄をもたらしたのである。
多種多様な機能をもつタンパク質
我々の呼吸、脳の活動や目・耳などの感覚器官の機能、その他あらゆる生命活動の営みを天然タンパク質がすべて引き受けており、その多種多様な機能ははかり知れず、広範囲にわたっている。これまで述べてきたようにタンパク質は生命の本質に直接関係する物質であるが、捉えどころのない性質が故に、その重大性が認識されていながらもDNA分子より注目されていないのが現状であり、まだまだ研究途上にあるといえる。私は、この極端に複雑で得体の知れないと思われがちのタンパク質のごく一部を、DNA分子を通じて垣間見ているのが現在の生命科学ではないかと考えている。
極端な例では、人の性格を遺伝子の塩基の変異で確率的に占うことがある。長い遺伝子の塩基配列でAがTに変異しているから、統計的に冒険心のあるヒトであると判断するような場合である。しかし、この変異するタンパク質はなんであるのか、どういう構造にどのような変化がおこり、そのタンパク質が周りのタンパク質にどのように働きかけて、冒険心の際立った性格を決定したかについては、タンパク質は全く何も語っていないし、未だ謎である。
遺伝子研究の最盛期のころ、DNAの研究が進めばタンパク質研究の未解決部分もいつかは明らかにされるだろう、という楽観的観測がなされ、「タンパク質の研究は終焉を迎えた」とする論評さえあったほどであるが、その後の遺伝子研究の推移をみると、タンパク質研究が終焉を迎えるような兆候は全くみられていない。