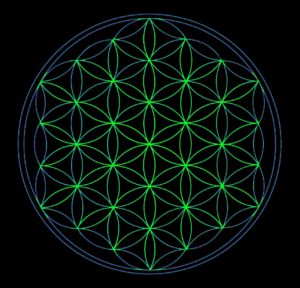2.短鎖ペプチド起源説
原始地球環境では、アミノ酸の直接熱重合によってミクロスフェアのような高分子のタンパク性物質が生成していたと考えられているが、アミノ酸が自然生成したのとは異なる原始地球環境下の海底の熱水噴火口で、短いペプチドが出現したことが有力視されている。私が考えたのは、この短鎖ペプチドが段階的な会合によって巨大化し、その過程で多様な機能を獲得し、天然タンパク質の原型が形成されることであった。しかもその場合、複製による再生産が可能なものでなければならなかった。
遺伝子が介入しないタンパク性物質の分子進化
従来から、タンパク質自身がタンパク質を複製することは不可能であると考えられてきた。タンパク質の複製には遺伝子の関与がどうしても必要であるとみなされ、タンパク質の起源はいつも遺伝子との関連から考えられていたためである。私は、この研究傾向が生命の起源の研究をややこしくしてきた一因であると考えている。そして、タンパク性物質は高分子核酸が出現する遥か以前に創生されたものであり、核酸が関係しない分子進化を想定する必要があると考えている。
私は第1部で短鎖ペプチド複合体の機能で、タンパク質の原型である短鎖ペプチドの複製が可能かを検討し、その可能性は十分にあると考えるようになった。即ち、複製可能の短鎖ペプチドの出現が生命誕生の重要な要因となり、機能をもつタンパク性物質が短いペプチド同士の複合体を形成することにより、段階的に巨大化したとする「短鎖ペプチド起源説」を考えた。この説は誰もが気がつけるものであるが、それを理論的に記述したものがこれまで私の知る限りはなかったことが不思議なくらいである。困難な合成が強いられる核酸とは異なり、短鎖ペプチドは地表や海底などの地殻が複合的に変動する複雑な原始地球環境で、比較的容易に合成が可能であったと考えられ、「短鎖ペプチド起源説」は充分に可能性があると考えている。
アミノ酸の自然生成と短鎖ペプチドの出現
私はアミノ酸の自然生成と並んで、この短いペプチドの出現が天然タンパク質の分子進化にとって、エポックメーキングだったと考えている。自然生成された数多くの短鎖ペプチドの中で、複合体を形成できるのはごく一部であり、この短鎖ペプチドが特異的に2~3個会合した複合体が“原始スープ”に多数蓄積され、それらの一部が核となり相互に会合し、その数を増やして大きな複合体構造が形成されたと同時に、それらの複合体が形成される間にも、会合している一部の短鎖ペプチドが解離し、再び別の親和性の高いペプチドと再会合するという、離合集散を繰り返しながら、より親和力と特異性の高い安定した複合体構造が形成されたと考えている。構成する短鎖ペプチドの種類や結合様式の違いで、複雑で安定した分子内構造を構築し、多種多様な機能を獲得しながら最終的に巨大な個別短鎖ペプチド複合体がつくられたと考える。原始無生物環境の末期(いつだかわからないが)、この巨大化した短鎖ペプチド複合体を構成している個々のペプチド構成体がペプチド結合で連結し、非常に長い一本鎖の原始タンパク質が形成された。この原始タンパク質は本質的に個々の短鎖ペプチド構成体の集積体であり、天然タンパク質の原型になったと考えられる。
タンパク質の無限性
一方、これまでもタンパク質の構造や機能については、膨大な研究が蓄積されてきた。既存のATP合成系、RNA 合成系、 DNA合成系、その他の複雑な反応に関与する酵素タンパクの構造をみるたびに、その複雑で巧妙な機構に驚嘆するほかはない。タンパク質は生物がどのような極限的環境でも適応できるように、最もふさわしい構造と機能を創り上げて困難な反応機作を創生してしまうことから、魔王的存在であると錯覚するほどである。自己制御機械とみなされている生命を起動している基本物質がタンパク質であることは間違いないが、タンパク質がどのようにして生命を作動しているかについては、ほとんど謎である。このように、現時点においても依然としてタンパク質はあまりにも謎に満ちた物質であり、それがどのように生命を運営しているかは、当分の間解明はし難いのかもしれない。
しかし、タンパク質の複雑で精巧な機構から、タンパク質の無限の能力を知ってしまった私は、第1部で示したように、原始前生物環境で触媒能力をもつ短鎖ペプチド鎖複合体が形成されること、当然このタンパク性物質が少なくともペプチド構成体のような短い鎖を複製できる能力をもつと考えたのである。原始前生物環境で、ペプチド複製能力をもつタンパク性物質が運営する原始的な複製装置が存在した可能性が、充分あったと考えられるのである。
遺伝子管理システムへの大転換
この短鎖ペプチド構成体を複製する原始タンパク性複製装置が自律的に作動し始めると、多種多様な物質の創生に係る反応を触媒する短鎖ペプチド複合体の生産は、より円滑に行われたと考える。しかし現在では、現存する細菌のごく一部に短鎖ペプチドのようなタンパク性物質の複製を行う機構が残っていようとも、それを含めてすべてのタンパク質の生合成は、現存の細胞でおこなわれる遺伝子情報管理システムで完全に操作されており、かつての鋳型的多短鎖ペプチド複合体系のようなタンパク性複製機構は全く排除されてしまっている。これは、原始無生物環境での旧体制の遺伝情報管理システムがある時期において戦略上の理由から完全に駆逐され、新しい高分子核酸が関係する遺伝子管理システムへと完全に大転換した結果であると考えている。
他の物質にはない擬態思想という異次元の本性をもつ短鎖ペプチドは、特定の物質と結合する際、自律的に自らの姿を変えてまで結合しようとする特性をもっており、このような結合機能をもつ短鎖ペプチドが、最優先的課題として自らを複製するという意図性を孕みながら原始地球環境に出現したと考えている。その紆余曲折の分子進化の結果、複製という意図性に基づいて、短鎖ペプチド複合体が鋳型的多短鎖ペプチド複合体系のペプチド複製機構を創生し、短鎖ペプチド構成体の安定した供給体制を確立したのであろう。
これまでによくいわれてきた、タンパク質自身がタンパク性物質の複製の担い手になり得ないという結論は、特定の塩基同士の相補的結合で自己複製するDNAとは異なり、特定のアミノ酸単体同士が相補的に結合できない、との結論から導き出されたものである。しかしタンパク質には、もともと生物の機能のすべてを遂行するために創生されたという意義があり、そのためには最小限で20種類のアミノ酸が必要で、これによって細胞のすべての機能を網羅している。DNAのように、遺伝子の収納や自己複製という専門性だけをもつわずか4種類の塩基で構成されているものとは、全くわけがちがうのである。多種多様な機能をもつタンパク質にとって、自らを複製することは確かに重要ではあるが、これはその多くの機能の中のごく一部であり、DNA分子の自己複製とは異なり、高分子核酸がない条件下では、独自の複製機構を創生しなければならなかったことは必然であっただろう。そこで、短鎖ペプチドは擬態思想をもって出現し、自らを複製したのである。