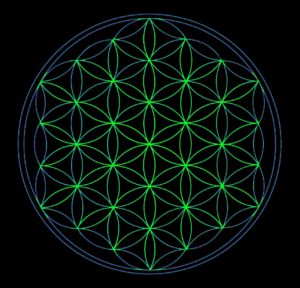1.これまでの総括とこれからの展望
第1部では、原始前生物環境でのタンパク性物質の出現と、それに伴う分子進化によって生命物質を含む有機物質の創生について述べた。この第2部は、それらの物質を基盤とした生命の誕生と生物進化について述べることにする。
生物進化を研究する方法
その前に、生物進化を研究する方法を考えてみたい。現在は化石や生物種間の遺伝子解析などを最大限駆使し、科学的な帰納的推理を展開した生物進化の方法論が成立している。しかし、原始前生物環境において、タンパク質の原型だと思われる短鎖ペプチドが存在し、それが複合体を形成し、さらにその複合体が短鎖ペプチドを複製できるまでに化学進化したこと、その後その複合体の複製機構の基本原理が現存の遺伝情報を収納しているDNA分子に引き継がれたなどとする、私がこれまで述べてきた分子進化仮説を裏付けるような物質は非常に限定されている。従って、原始前生物環境の分子進化を知る手がかりは、その進化で生じた現在のタンパク質、高分子核酸、その他の生命物質に求めなければならない。それらの物質に関しては、これまでに膨大な量の研究成果が蓄積されている。その成果を駆使して原始前生物環境での分子進化を帰納的に推理し、原始前生物環境を遠望するしかない。この分子進化のたどりついた先が奇跡的な生命の誕生であり、この生命の誕生が太陽系第三惑星である地球の歴史での、最大のエポックメイキングになったのである。現在はこの生命の起源の謎に挑戦できる幸せな時代であるのかもしれない。
私は、現在の生物を運営している主要な物質は、他の天体に存在しない、原始地球前生物環境から一貫して分子進化を牽引してきた、多様な機能をもつタンパク性物質であると考えている。さらに、その遥か後にそのタンパク質がつくったDNA分子が加わって、細胞の原型が形成されるのに伴って、基本的にタンパク質とDNAの協同作業で現在の生命が誕生したと考えている。生命の誕生の場は基本的に細胞で、この狭い閉ざされた半透膜の空間で営まれる物質代謝と遺伝装置の創生であったこと、それらの根底を支えたのがタンパク質の存在であったことは間違いないと思っている。これが、私が生命の起源を「タンパク質ワールド」とする所以である。
天然タンパク質の起源
ここで一旦、私が考えた原始地球環境で、自然生成した短鎖ペプチドを原型としたと考えられる天然タンパク質が、どのような分子進化の末、出現したかを総括的に述べてみたい。まず、「タンパク質ワールド」仮説の主役であるタンパク質構造の創生に必須なアミノ酸類は、原始地球創生期の混沌とした複合的な自然環境下で奇跡的に出現したとする自然生成説、そのほかにも地球外小惑星からの隕石飛来説など諸説がある。タンパク質の起源については、先に述べたミラーの実験のような、すべての人を説得させるような有力な説がなかったことは不思議である。私が本書の第一部で述べたのは、タンパク質の起源に関する一つの私案である。
私は、太陽系第三惑星地球に短鎖ペプチドが出現したことが、この惑星に生命が育む決定的な要因になったと考えている。即ち、アミノ酸は自然生成された多くの有機物質の一つと見なすことはできるが、そのアミノ酸類がペプチド結合で重合した短鎖ペプチドは稀有な性質を持つ物質であり、他の有機物質にはない異次元の擬態思想や分断化思想をはらみながら、原始地球に出現したのである。擬態思想をもつ短鎖ペプチドが、他の多くの有機物質と自律的に結合する可能性を持ったことに、生命誕生の根源があると考えている。
短鎖ペプチドの持つ結合特異性
短鎖ペプチドの擬態思想の恐るべき点は、どのような物質に対しても無作為に結合できるのではなく、結合する対象を厳しく制限するという結合特異性を持っていたことであった。即ち、一定の短鎖ペプチドは厳しく限定された物質としか結合できないことから、結合対象物質の種類が増えれば、それに比例して、対応する短鎖ペプチドの種類も増加しなければならないという必然性が生じたのである。これは、分断化思想でのタンパク性物質の多様化で克服されたと考えられる。原始地球におけるアミノ酸の種類は、現存の20種よりは少ないといわれているが、アミノ酸が構成する数が十数個以下の短鎖ペプチドが、この頃に種々雑多生成されたことになる。ただし、そこで生成された雑多なペプチドのすべてが物質と結合できるわけではなく、その中のごく一部が結合に関わったであろうと推測している。また、自然生成する有機物質の種類が増加すると、物質と結合できる短鎖ペプチドも当然相対的に減少することになるが、先に述べたように、短鎖ペプチドの会合において、多数の短鎖ペプチドの数と組み合わせで形成される複合体の種類が膨大になることで解決されると考えている。当時産出された複合体の種類は、存在していた物質の種類よりもはるかに多く、その後に新規に生成される物質に対しても十分に対応できるほど、余裕があったと考えている。
別の面からみると、現存のタンパク質が物質と結合する部位の構造は、ほぼ短鎖ペプチドの長さのレベルで結合しており、これから判断すると、原始前生物環境の短鎖ペプチドが物質と結合する場合も、ほぼ同じ長さであると考えられる。これをもっと深く考えてみると、10数個のアミノ酸からなる短鎖ペプチドが重要であるという理由は、短鎖ペプチドが単独では固定した構造はとらず、遷移性の数種の混成構造体となって存在する事が知られているからである。この遷移性の短鎖ペプチドがどのような構造体に固定されるかは、ペプチドを取り巻く構造環境に影響され、タンパク性物質の擬態思想が生じる原因ともなっていると考えている。例えば、不規則構造(disordered conformation)のペプチドは、対象物質と結合すると固有の立体構造に変化するという報告がある(文献:Nakamura N., Higo J. et al.: free energy landscapes of peptides by enhanced conformational sampling)。この不規則構造が対象物質の形とぴったり結合すると、固定化すると考えられるのである。即ち、あらゆる多様な不規則構造の中で、最適の結合条件を示したものだけが固有の構造に固定化されるのであろう。原始前生物環境では、短鎖ペプチドの擬態思想が、現在のタンパク質よりも大規模で広範囲に行われていたのではないかと考えている。